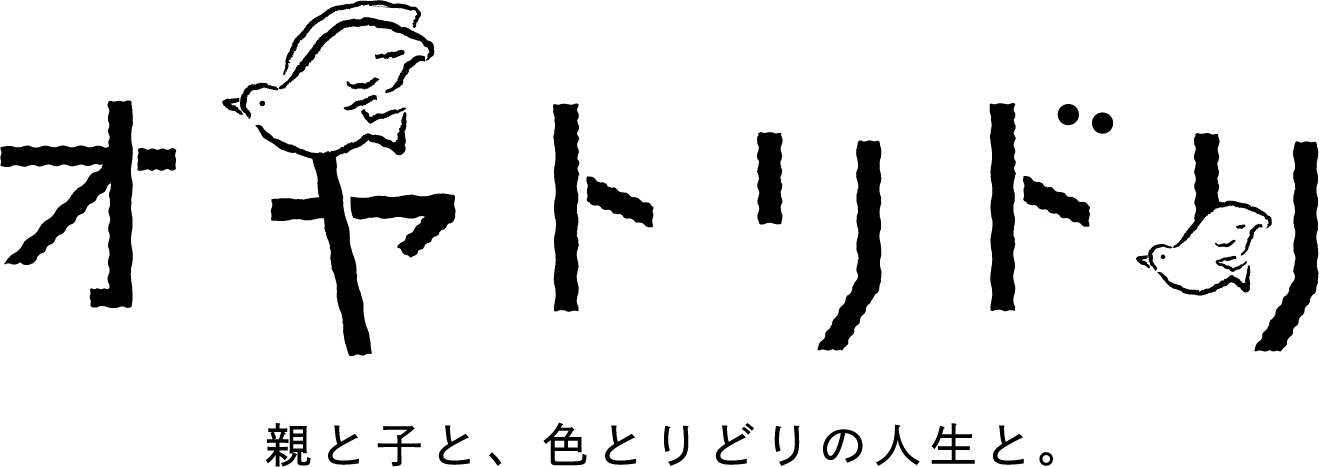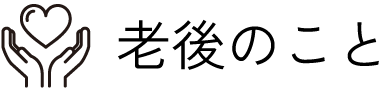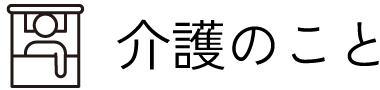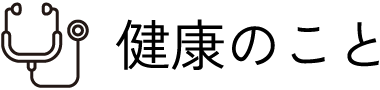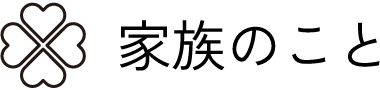32歳で介護を経験した私。家族を背負って生きるのはやめた
―ある日突然、介護の海に放り出された。
それは、驚きと絶望と戸惑いとともにやってきた。果てしなく広くて、暗い海。泳ぎ方もわからなければ、岸も浜も見えない。この海はどこまで続くのだろう?
父がアルツハイマー型認知症であるという診断を受けたとき、私は31歳、父は63歳だった。65歳未満で発症すると、認知症は「若年性」という名称が頭につくらしいと知ったのもこのときだ。
父の場合、「おかしいな?」という予兆があり、家族から見たら明らかに以前の父と違う点が増えてきても、診断が下りるまでは5年以上のグレーゾーン期間があった。
ようやく診断が下りた、と不思議と胸を撫で下ろしたくなるような心境だった翌年、家族に激震が走った。
母のがんが発覚したのだ。
母のがんは見つけづらい箇所にあり、発見時点ですでに他への転移がみられ、ステージ4と診断された。
母が死んでしまう? そんなわけない! 到底信じたくない事実が恐怖となって私を襲った。
同時に、「母がいなくなったら私が父の面倒をみるのだろうか?」という、確かな予感と不安が押し寄せてきた。
私の身に本当の意味で「介護がやってきた」と感じたのは、父の診断が下りたときではない。母のがん発覚をきっかけに、父の介護の中心人物になったときだった。そのときの私は、32歳。

4歳上の兄と9歳下の弟にはさまれた長女、フリーランスの私。当時、何の因果か実家に出戻っていた矢先のできごとだった。
母の病気が発覚するまでは、父の介護の担当は母だと、パーテーションを一枚隔てたような距離をとっていて、親のこととはいえ、どこか他人事のように思っていた。
しかしこうなっては、実家で同居している女性、しかも時間の調整がきくフリーランスの私が介護にとらわれる可能性が高いことは予感できた。そしてそれを危惧していたのは母だった。
ドラマのように具体的な余命を告げられるでもなく、どのくらい母が生きられるのかは誰も予測がつかない。
もしかしたらもう1ヶ月後には母がこの世から去ってしまうのでは? というあてどない焦燥感にかられる。いずれにせよ残された時間は、そう長くないのかもしれない。
認知症の診断が下りる前後は、父と外出しようと言っても待ち合わせをすっぽかされたり、現れたかと思えば季節感のずれた服装をしていたりと、あきらかにそれまでの父とは違う行動が多々あった。
離れて暮らしているうちは父のそのすっとぼけた言動を笑って、一歩引いて父を支える気持ちの余裕があった。
だけど一緒に暮らし始めてみると、外出もしなくなった父はずっと寝巻きのままでいたり、話すことといえば目の前でかかっているテレビ番組の話題ばかり。
「昔のお父さんはこうじゃなかったのに……」と、娘として失望してしまう場面が多々あった。
それに加え、入浴を億劫がるようになった父に何度も声を荒げなければいけない毎日にも嫌気がさす。
自分が認知症であるという病識がない父は、私へも母に対しても「自分のことは自分でできるんだから放っておけ」という態度をとり、ついついいら立ってしまう。
平和な家族として暮らした32年間が一気に覆るほどに、今まで感じたことのない不穏さが家の中を漂い、息が詰まる想いがした。こんな状態が続いたら、私はあっという間に潰れてしまう。母がいなくなったらと思うと、なおさらだ。

(おしゃれ好きだった父が一日スウェット姿でいるのを見るのは悲しかった)
少し時は飛んで、現在の話になる。いきなり介護がやってきた32歳から6年が経ち、私は38歳になった。
母は2018年の年末に他界。父はコロナ禍前の2019年に有料老人ホームに入居し、兄弟での在宅介護はその時点で終了した。
今回の連載のお話をいただいたとき、現在進行形で在宅介護をしているわけでもない今の私が何を書けるだろう?誰に読んでほしいだろう?と考えた。
そして頭に浮かんだのは、32歳から33歳くらいまでの一番戸惑い続けていた頃の私の姿だった。
どうして自分の身にこんなことが起こったのだろう。誰を責めることもできない言いようのない理不尽さや怒りや、悲しさ。この気持ちを同年代の友人に話しても困らせてしまうだろうと思うと、話すことも難しかった。
似た境遇の人がいないかと本を探してみても、介護の話の主人公は大抵私よりも世代が上だったし、介護サービスの対象者も80代以上を見据えたものが多く、当時60代の父のための情報を得るのは難しい。
本が見つからない、求めている情報に辿り着けない、ただそれだけで孤独を感じていた、あのとき。
あのときの私が知りたかったこと、求めていたことって、なんだっけ。

介護は、家族だけで解決できないことばかり起こる。自分でコントロールしきれない出来事も続く。
その中で、自分が求めるタイミングで必要な情報に適切に出会えたときは、心理的にも、物理的にも救われた。それは、広くて先が見えない海から、「あそこまで行けばなんとかなりそう」と思わせてくれる灯台のあかりだった。溺れかけているときに手を差し伸べてくれる存在。
ひとつひとつを知っていくことで、私はこの海を息長く泳ぎ続けるための方法を少しずつ習得してきた。
どこでも仕事ができる職種でも、在宅ではなくシェアオフィスを借りて仕事をするとか。すべてを忘れて銭湯に行って、ほっとする時間を作るとか。好きなアーティストのライブは最優先で行くとか。
「好き」や「楽しい」は、一番ないがしろにしてはいけない、大事な息つぎポイントだった。
「好き」を諦めない方法を選択しないと、私はこの先父を恨んだり、嫌いになってしまうかもしれない。暗い海の真ん中で潜水をし続けても、息はそう長く続かないものだから。
そう、だから少しずつ楽しく、浮き上がりたかった。キラキラ眩しすぎるほどではない、ほのかに明るく楽しそうな、希望を感じる情報に触れたかった。案外近くに仲間がいるかもしれないことに、気が付きたかった。
現在も私は、複数の肩書きを持つフリーランスとして生きている。実は付け加えると、2021年に東京から岩手県の紫波町という町に移住し、地域おこし協力隊という職業も兼務している。
32歳のときの私に「あなたは6年後、岩手に住んでいます」と言ってもおそらく信じないだろう。
なぜ移住したのかを一言では言うのは難しい。
だけど亡き母が生前一番心配していた、家族仲が壊れてしまうことを防ぐために、私たち家族が選んだのは「自分たちの人生を犠牲にしない」介護だった。
父が暮らす東京を離れ、長女でキーパーソンの私が岩手に移住することは、その一つの表れだとも言えるかもしれない。
6年経っても、岩手に引っ越しても、私は今も介護の海の中にいる。
だけどその海は、数年前のような暗いものではない。どこかでまた大きな波に襲われるかもしれないけれど、視界はおおむね良好。ただ海辺のまちに暮らしているような、私の日常の風景の一部になった。
この連載では、これまでの経験を振り返りながら、ときに他の介護者の方のお話も伺い、重たい荷物を背負いすぎず、この先も続く介護の海を泳ぎ続けるための取り組みを紹介していけたらと思う。
あのときの私へ、そして今、あるいは少し先の未来に、家族の重い荷物を抱えているあなたへ。少しでも荷物を軽くするヒントが届けられるようにと願いながら。