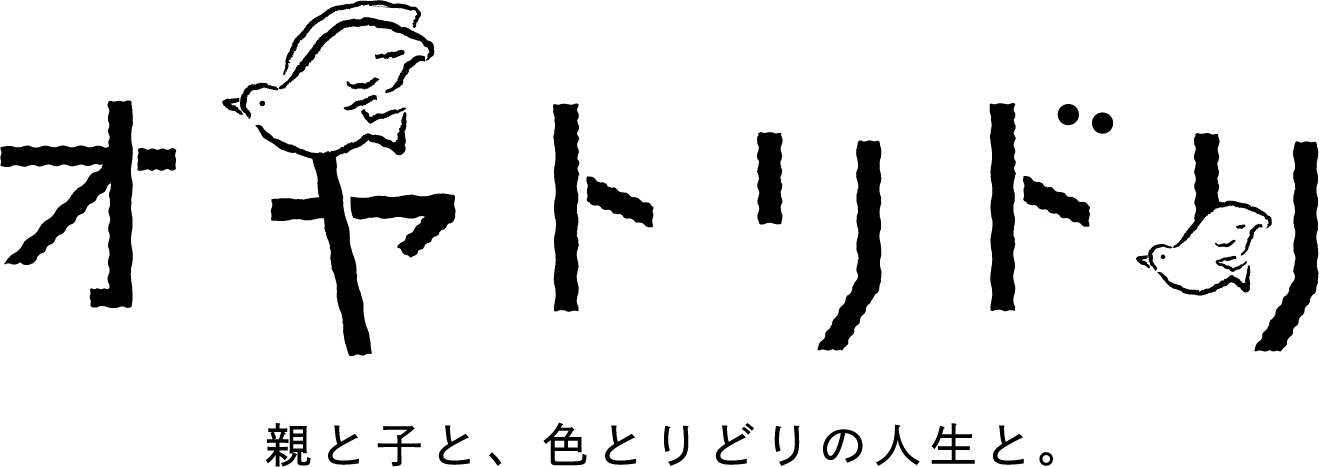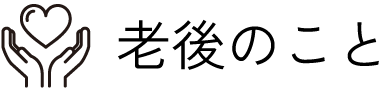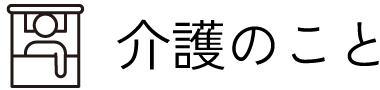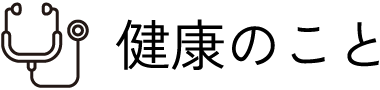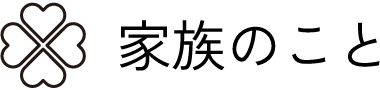この連載では、ケアマネジャーである筆者が、介護に関する知識や情報、親の介護を少しでもラクにするためのヒントをわかりやすくご紹介します。
Q:要介護認定を受けて、介護保険サービスを利用することになると、「ケアプラン」を作成する必要があると聞きました。ケアプランとはどのようなもので、何のために作成するのですか?
A:ケアプラン(介護サービス計画書)は、要介護・要支援者が介護保険を利用してサービスを受ける際に必要となる書類です。
ケアプランには要介護1〜5と認定された人のために作成する「居宅サービス計画」や「施設サービス計画」、そして要支援1〜2と認定された人のために作成する「予防サービス計画」(介護予防ケアプラン)があります。
今回は、ケアプランについて、作成する理由や作成時の注意点をご紹介します。
1.ケアプランを作成する理由
ケアプランとは、介護サービスをどのように利用するかを決める介護サービス計画書のことです。
利用者の課題(ニーズ)や目標、利用する介護サービスの内容などが記載されています。
ケアプランを作成することで、利用者と家族の生活の意向と解決すべき課題(ニーズ)を明らかにでき、その解決策や改善策を分析できます。
それにより、利用者やその家族は、心身状態や生活状況に合った快適な介護サービスを受けられるようになるのです。
なお、ケアプランの作成費用に利用者の負担はなく、 全額介護保険から賄われます。
2.ケアプランを作成できる人
ケアプランは、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するのが一般的です。
要介護1〜5のケアプランは、居宅介護支援事業所や介護保険施設にいるケアマネジャーが、
要支援1・2の介護予防ケアプランは、地域包括支援センターにいるケアマネジャーなどが作成します。
一方で、ケアプランは、利用者やその家族で作成することも可能です。
これを「セルフケアプラン」と呼びます。
セルフケアプランでは、利用者やその家族がサービス事業者と直接やり取りができるので、自由度の高いケアプランが作成できます。
しかし、ケアプラン作成に必要な情報の収集や複雑な事務手続きは、すべて自分たちで行わなければなりません。関係者とのやり取りや専門的な知識が必要となるほか、市区町村の担当窓口がセルフケアプランの対応に慣れていない場合もあります。
そのため、ケアマネジャーに依頼して作成してもらう方が、スムーズに介護生活をスタートできるでしょう。

3.ケアプランの内容
要介護者向けのケアプラン(介護サービス計画書)の書類は、全部で7表あります。
そのうち、第1〜第3表の内容が、ケアプランを立てるうえで重要となります。
参考:厚生労働省「居宅サービス計画書」
■第1表:計画書全体の方向性を示す
【主な内容】
利用者本人の名前、住所、要介護度、認定日などの基本データと、利用者や家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針を記載します。
■第2表:計画全体の中核として、給付される介護保険サービスの根拠を示す
【主な内容】
たとえば「一人でトイレに行けるようになりたい」といった利用者の課題(ニーズ)とそれを解決するための短期・長期目標、課題を実現するための具体的な介護サービスの内容(種類、頻度、期間)を記載します。
■第3表:介護サービス計画の1週間のタイムスケジュール
【主な内容】
週単位の介護サービスと利用者の活動を記載します。利用者はこのスケジュールに沿って介護サービスを利用することになります。
4.ケアプラン作成とその後の流れ
次に、ケアプラン作成とその後の流れを確認しましょう。
【ケアプラン作成とその後の流れ】
①ケアマネと利用者・家族が面談
②ケアマネがケアプラン原案を作成
③利用者・家族が確認
④サービス担当者会議で決定
⑤利用者・家族への説明と同意
⑥ケアプランの完成
⑦サービス提供事業者と契約
⑧介護保険サービスの利用を開始
⑨ケアマネの定期訪問
⑩ケアプランの見直し
①ケアマネと利用者・家族が面談
ケアマネジャーが利用者や家族と面談をして、身体状況や生活環境などを把握します。
利用者や家族はどんなサービスを受けたいか、しっかりと要望を伝えましょう。
②ケアマネがケアプラン原案を作成
ケアマネジャーが本人や家族からの情報をもとに解決すべき課題や目標を決定して、ケアプランの原案を作成します。
③利用者・家族が確認
ケアマネジャーがケアプラン原案の内容を利用者と家族に説明し、希望と相違がないか確認します。
④サービス担当者会議で決定
サービス担当者会議はケアマネージャーが主催します。
本人と家族のほかに、サービス提供事業者や主治医、看護師などの関係者が出席し、介護サービスの中身や方針などの情報を共有します。この話し合いにより、ケアプランの内容が確定します。
なお、この会議はケアプランの見直しが必要となったときや要介護度が変わったときにも開催されます。
⑤利用者家族への説明と同意 ⑥ケアプランの完成
ケアマネジャーからケアプランについて説明を受け、同意をしたらケアプランの完成です。
⑦サービス提供事業者と契約 ⑧介護保険サービスの利用を開始
利用者が各サービス提供事業者と契約をして、サービスが開始されます
⑨ケアマネの定期訪問
サービス開始後もケアマネジャーは定期的に利用者の状況を確認します。
⑩ケアプランの見直し
必要があれば、ケアマネジャーがサービスの見直しなどを行います。

5.ケアプラン作成時の注意点
介護保険サービスは、ケアプランの内容に沿って提供されるため、ケアプランに記載されていないサービスは、あとから要望を伝えても利用することができません。
そのため、ケアプランを作成する際には、ケアマネジャーに任せきりにするのではなく利用者や家族も一緒に参加して作り上げていくことが大切です。
ケアマネジャーとの面談では、日常生活での不安や不便に思っていることをためらわず伝えましょう。
「こんなことを言っても大丈夫だろうか」と思うことでも、ケアマネジャーには守秘義務があるので安心して相談してください。それが、より良い介護生活の実現につながります。
【ケアマネジャーに伝えるポイント】
・利用者本人の心身の状態
・家族など介護者の状況
・本人と介護者の生活パターン
・本人や家族が希望する生活
・介護サービスに期待すること
・介護サービスに使える予算
さらに、ケアマネジャーが作成する「ケアプラン原案」の内容をしっかり確認することも重要です。
以下は、ケアプラン原案のチェックポイントです。
【ケアプラン原案のチェックポイント】
・本人の状態が良くなりそうか
・介護者の負担が軽くなりそうか
・無理のないスケジュールになっているか
・経済的な負担が大きすぎないか
・要支援の場合、介護予防につながっているか
6.まとめ
介護保険を利用して介護サービスを受けたい場合は、ケアプランの作成が必須です。
ケアプランの作成は、ケアマネジャーに任せきりにするのではなく、利用者や家族も主体的に関わり、作り上げていくことが大切です。
また、どんな生活を送りたいか、どんなサポートが必要かを考えながら、現在の状態を維持し、改善するための方法やサービスを選ぶようにしましょう。
最後に・・ - オヤトリドリ編集部より 書籍のご紹介 –
オヤトリドリで日頃から介護の知識や現場のリアルをわかりやすく伝えてくださっているケアマネジャーの中谷ミホさん。このたび、中谷さんが著者として携わられた書籍が出版されました。
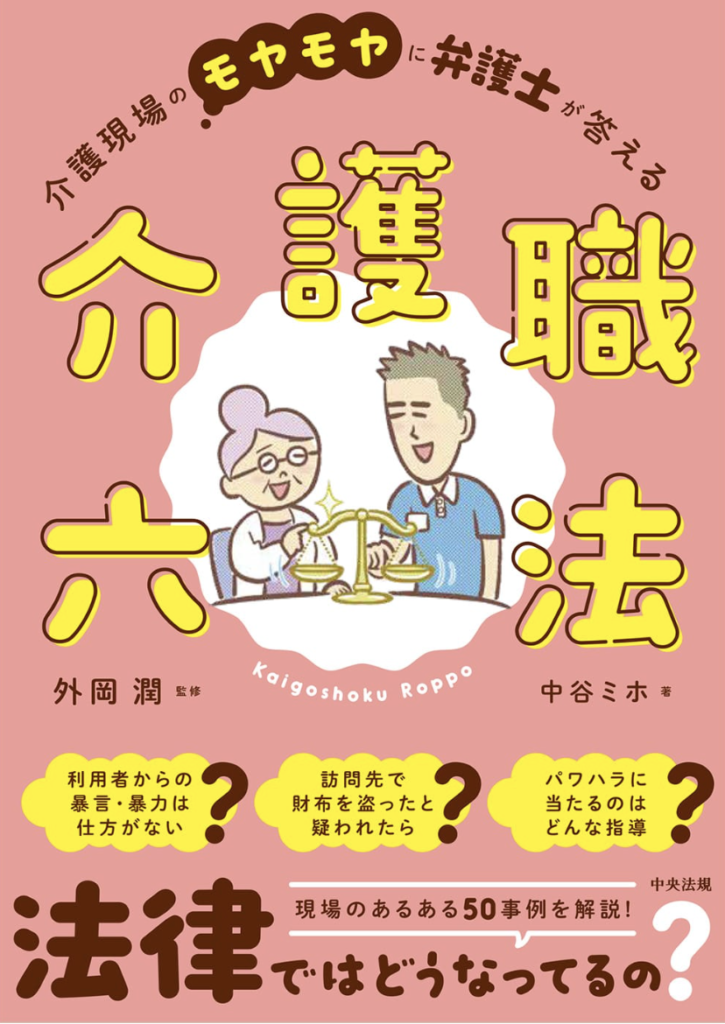
『介護職六法 介護現場のモヤモヤに弁護士が答える』
(監修:外岡 潤/著:中谷 ミホ)
介護の現場では、介護保険法や高齢者虐待防止法、個人情報保護法など、実に多くの法律が関わっています。しかし、現場で働く方々にとって、その「法律の根拠」はなかなか見えにくいもの。本書は、弁護士の外岡先生の知見をもとに、中谷さんが長年の介護現場での経験を踏まえて「介護職の目線」でやさしく解説しています。
法律を学ぶことで、事業所のルールの背景が理解できたり、トラブル時の対処のヒントを得られるなど、日々の業務に安心感が生まれるはず。研修やコンプライアンスの学びにも活用できる実用的な一冊です。
介護職に興味のある方や、現場での法律とのかかわりに関心のある方は、手に取ってみてはいかがでしょうか・・☆